e-Japanのあした 2005
<e-Japanのあした 2005>15.自律的移動支援プロジェクト(上)
2004/12/13 16:18
週刊BCN 2004年12月13日vol.1068掲載
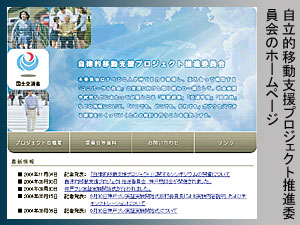 先月16日、東京大学安田講堂で、シンポジウム「第2回ユビキタス場所情報システム・シンポジウム」が開催された。自律的移動支援プロジェクトのリーダー、坂村健・東大大学院教授の基調講演のあと、パネルディスカッションには国交省前技監の大石久和・財団法人国土技術研究センター理事長、ITS(高度道路交通システム)研究で著名な川嶋弘尚・慶応義塾大学教授が出席して、プロジェクトの重要性について話し合った。IT業界において坂村教授は超有名人だが、大石理事長はほとんど知られていないかもしれない。ITS政策を積極的に推進する国交省道路局長を経て、技術官僚のトップである技監を今年6月に退官したばかりで、現在は早稲田大学大学院客員教授として「国土経営・国土学」の教鞭も執る国土学の第1人者である。ITにも見識が深く、今回のプロジェクトの仕掛け人だ。
先月16日、東京大学安田講堂で、シンポジウム「第2回ユビキタス場所情報システム・シンポジウム」が開催された。自律的移動支援プロジェクトのリーダー、坂村健・東大大学院教授の基調講演のあと、パネルディスカッションには国交省前技監の大石久和・財団法人国土技術研究センター理事長、ITS(高度道路交通システム)研究で著名な川嶋弘尚・慶応義塾大学教授が出席して、プロジェクトの重要性について話し合った。IT業界において坂村教授は超有名人だが、大石理事長はほとんど知られていないかもしれない。ITS政策を積極的に推進する国交省道路局長を経て、技術官僚のトップである技監を今年6月に退官したばかりで、現在は早稲田大学大学院客員教授として「国土経営・国土学」の教鞭も執る国土学の第1人者である。ITにも見識が深く、今回のプロジェクトの仕掛け人だ。「人口4600万人の韓国でもソウル-釜山間に片側4車線の高速道路を整備したのに、日本では第2東名高速道路の整備もなかなか進まない状況。狭い国土という制約もあって既存道路の拡幅も難しい。道路交通の安全や効率を向上するには、別の形で何らかの支援を行う必要があると考えたのが、ITSに取り組むきっかけだった」と、大石理事長は振り返る。国交省がITSに取り組んでから10年以上が経過して、ETC(自動料金支払いシステム)の普及率も20%を超えて渋滞緩和などの効果も出てきたところだ。
大石理事長が技監時代に打ち出した新しい国土交通政策のキーワードが「ユニバーサル社会」。国交省では、90年代から“バリアフリー”の考え方に基づいて障害者に対しても障壁がなく参画できる社会の実現をめざしてバリアフリー住宅や段差の少ない道路などの整備を進めてきた。こうした考え方をさらに進め、誰にとっても優しいユニバーサルデザインの考え方に基づいた社会づくりを進めようというわけだ。
「すでに日本の生産人口は95年にはピークアウトした。今後、少子高齢化が急速に進展するなかで、北欧のような国民負担率7割もの社会を日本では誰もが望まないだろう。そうであるなら、高齢者や女性が能力とやる気を発揮して積極的に社会進出することを支援する国民総参加型社会を構築していく必要があるのではないか」。そうした視点から、障害者や高齢者を含めた全ての人が、自立し、安心して暮らし、持てる能力を発揮できる“まち”をめざして総合的な国土交通政策の構築が進められ、具体策として今回の自律的移動支援プロジェクトも位置付けられている。
「河川堤防や道路などの膨大な既存構造物を保守管理するのに人間の目による点検はもちろん重要だが、今後の人口減少社会を考えれば、構造物自体をインテリジェント化し、何か不具合が生じた時には自ら知らせるような仕掛けも必要だろう」。年金・医療問題、さらに増税の論議も本格化するなか、今後の少子高齢化社会をどう乗り越えていくのか。その問題解決のツールとしてITをどう活用していくのか、との視点がますます重要になっている。
- 1














