OVER VIEW
<OVER VIEW>変革へのターニングポイント迎えた、世界ハイテク産業 Chapter2
2004/02/09 16:18
週刊BCN 2004年02月09日vol.1026掲載
新しいハイテク産業発展の背景
■ハイテク産業、モジュラー、インテグラルの2つの型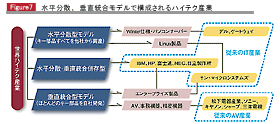 世界のハイテク業界ベンダー経営タイプについては、典型的に2つのモデルがあることはよく知られている。1つはキー部品を他ベンダーから調達して製品を組み立てる水平分散型モデルで、その典型はインテルプロセッサとマイクロソフトOSによって組み立てられるパソコン、インテルサーバーのWintel仕様が中核だ。
世界のハイテク業界ベンダー経営タイプについては、典型的に2つのモデルがあることはよく知られている。1つはキー部品を他ベンダーから調達して製品を組み立てる水平分散型モデルで、その典型はインテルプロセッサとマイクロソフトOSによって組み立てられるパソコン、インテルサーバーのWintel仕様が中核だ。一方、半導体を含むほとんどのキー部品を自社で開発生産し、製品を仕立てるのが垂直統合型モデルだ。IT分野では当モデルを維持するベンダーは、Wintel製品以外の大・中型サーバー、ストレージなどエンタープライズ商品が主力である(Figure7)。
しかし、エンタープライズ市場が中心であっても、多くのベンダーはWintel商品も生産するので、有力なIBM、HP、さらにわが国の富士通、NEC、日立製作所は、両モデルの併存型である。
一方同じハイテクでもAV、事務機器、精密機器を中心とする松下電器産業、ソニー、キヤノン、シャープ、三洋電機などは、典型的垂直統合型である。わが国が世界で圧倒的シェアをもつ薄型テレビ、デジタルカメラ、DVDレコーダは部品まで自社開発であるので、他国ベンダーとの技術格差が大きい。
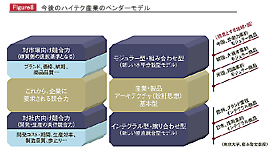 一方、デル、HPなどがデジタルAVへ参入したが、これらITベンダーはパソコンと同じような水平分散モデルでAV市場へ参入した。これで初めて、AV市場で両モデルの競争が始まる。今後のハイテクベンダーのモデルに関して東京大学藤本隆宏教授は、アーキテクチャ基本型としてモジュラー型とインテグラル型を紹介する。既存部品の組み合わせで計画製品の機能を実現するのがモジュラー型だ。
一方、デル、HPなどがデジタルAVへ参入したが、これらITベンダーはパソコンと同じような水平分散モデルでAV市場へ参入した。これで初めて、AV市場で両モデルの競争が始まる。今後のハイテクベンダーのモデルに関して東京大学藤本隆宏教授は、アーキテクチャ基本型としてモジュラー型とインテグラル型を紹介する。既存部品の組み合わせで計画製品の機能を実現するのがモジュラー型だ。一方、狙う製品性能から部品などを最適設計をするのがインテグラル型だ。これらはそれぞれ従来の水平分散と垂直統合に類似したベンダーの区分である。さらに同教授は今後の企業競争力も市場に向ける力と社内の力の2つに分けられると説明する。
現在のハイテク業界を見ると、モジュラー型企業は当然、価格、ブランドなど市場向け競争力強化を指向している。一方、インテグラル型企業は開発力や生産力強化など社内競争力発揮に力点を置いているようだ(Figure8)。
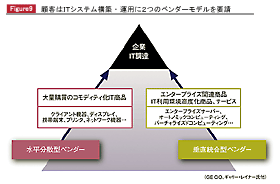 ■米国でも期待高まるハイテクのデジタルコンバージェンス
■米国でも期待高まるハイテクのデジタルコンバージェンス米国大企業IT部門ではIT調達先を大量購入品とエンタープライズ製品で異なるタイプのベンダーに分けるという流れが強くなっている。ゼネラル・エレクトリック(GE)のギャリー・レイナーCIOも、「企業にとっては2の型のベンダーがある方が調達コストを下げる」という(Figure9)。
さて、デジタルコンバージェンスを見据えた今後のハイテク業界変革の見方は、米国でもわが国とほぼ同じだ(Figure10)。
04年以降、米国ハイテク業界で今後の変化を表わすキーワードは、デジタルコンバージェンス、パーベイシブ(ユビキタス)コンピューティング、エムベデッドテクノロジーの3つといわれている。
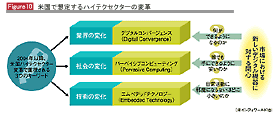 一方、米インフォワールドは、これから数多く誕生する新しいデジタル機器に対するユーザー関心は、「何ができるのか」、「安いのか」、「十分小さいのか」の3つだと指摘する。企業もコンシューマもその関心は同じようだ。このユーザーの関心に、業界、社会、技術の変化がどう対応できるのか、これが今後の課題のようだ。
一方、米インフォワールドは、これから数多く誕生する新しいデジタル機器に対するユーザー関心は、「何ができるのか」、「安いのか」、「十分小さいのか」の3つだと指摘する。企業もコンシューマもその関心は同じようだ。このユーザーの関心に、業界、社会、技術の変化がどう対応できるのか、これが今後の課題のようだ。さて、「現在、世界規模で進展しているハイテク産業の大きな変化は70年代から80年代に起きた第1次デジタル革命の経緯と類似している」と米商務省などは解説している。同省によると、70年代はオフィスよりむしろホーム市場のビデオゲーム機などが先導役となってハイテク化が進み、これでパソコンが出現した。そして90年代後半、今度はパソコンが先導役となって通話機にすぎなかったモバイルテレホンにデジタル革命が起き、短期間でテレホンがワイヤレスネット機器、デジタルカメラ、カラービューワ、デジタルウォーレット(財布)という多機能に変身した。
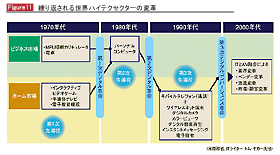 そして現在進行中のコンバージェンス現象は、この変身したモバイルテレフォンが先導役となった。こうして見ると、ハイテク業界には常に10年から20年のサイクルで大きな変革が起き、ハイテク市場拡大の牽引力が次々と代わってきたことがわかる(Figure11)。
そして現在進行中のコンバージェンス現象は、この変身したモバイルテレフォンが先導役となった。こうして見ると、ハイテク業界には常に10年から20年のサイクルで大きな変革が起き、ハイテク市場拡大の牽引力が次々と代わってきたことがわかる(Figure11)。米国の著名技術家、ロジャー・マクナミー氏は次のように解説する。「パソコン出現以来これまで、世界のハイテク市場の主役はITであった。しかし現在進んでいるデジタルコンバージェンス潮流で、ITに代わってAVが脇役からハイテク市場拡大の中心に躍り出た。もはや企業ITシステムでもデジタルAV活用を工夫する時がきた」
■ポスト産業資本主義がデジタル社会の背景に
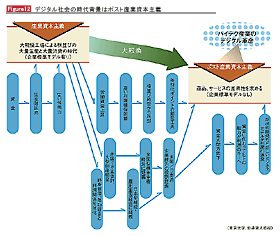 東京大学の岩井克人教授は、「現在先進国経済はこれまでの産業資本主義からポスト資本主義の転換期にある」と説く。どうやら今起きているハイテクでのデジタル革命の背景も、この時代転換に求められるのかもしれない(Figure12)。
東京大学の岩井克人教授は、「現在先進国経済はこれまでの産業資本主義からポスト資本主義の転換期にある」と説く。どうやら今起きているハイテクでのデジタル革命の背景も、この時代転換に求められるのかもしれない(Figure12)。産業資本主義は大量生産と大量消費時代を招いた。そこでは巨額資金が世の中を支配した。しかし時代が変化し、資本主義は変化し、それぞれの企業が横並びではなく差別化ポイントを創意しなければ、利潤と結びつかない変化が起きた。この間には米国流の株主主権やわが国の組織・雇用重視の企業ガバナンスに疑義が生じた。これからは資金に代わって、ヒトの能力が創り出す新しい技術と、新しいビジネスモデルによってのみ、高い利潤を手にすることができる時代となるようだ。これを同教授はポスト産業資本主義だと説明する。
この時代、顧客は商品、サービスの差異性に強い関心を払う。まさに今世界で起きつつあるデジタル革命は、ポスト産業資本主義を背景にしていると考えると理解しやすい。新しい技術が次々と新デジタル商品を生み、これがゼロスタートから急速に市場を拡大しているからだ。デジタルAVで先行するベンダーが好決算をすることが、この証ともなろう。
- 1














