OVER VIEW
<OVER VIEW>オンデマンドで世界市場席巻に挑むIBM Chapter1
2004/01/05 16:18
週刊BCN 2004年01月05日vol.1021掲載
ベンダーを駆り立てる市場の変化
■世界有力ベンダー、一斉に新ITコンセプトを発表02年10月、IBMの新戦略「e-ビジネスオンデマンド」発表と相前後して、世界の有力ベンダーは一斉に、ビジネス要請に従って柔軟に変化できる新しいITコンセプトを次々と打ち出した。
各ベンダーによって、その呼称は異なるものの、狙うところはほとんど同じだ。この呼称が多く混乱があるため、米ガートナーはこれらを「動的に変化するIT」という意味をこめて「ダイナミックエンタープライズシステム」と総称することも提唱している。03年に各ベンダーは提唱コンセプトを徐々に具現化するハード、ソフトの製品群やITサービスを発表し、04年以降オンデマンドは業界の強い潮流になることがはっきりしてきた。
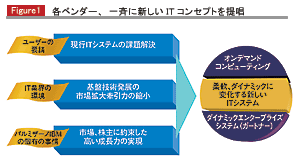 わが国でも大企業を中心にオンデマンドに対する関心が高まっている。IBMのオンデマンド採用ユーザーリストにも東京三菱銀行、小糸製作所、福山通運などが名を連ねている。IBMに対抗するため、富士通、NEC、日立製作所も自社コンセプトや関連商品の市場キャンペーンを積極化している。
わが国でも大企業を中心にオンデマンドに対する関心が高まっている。IBMのオンデマンド採用ユーザーリストにも東京三菱銀行、小糸製作所、福山通運などが名を連ねている。IBMに対抗するため、富士通、NEC、日立製作所も自社コンセプトや関連商品の市場キャンペーンを積極化している。この新しいIT業界の潮流が急速に勢いづいたのは、ユーザーの要請とIT業界の環境変化がもたらしたものと考えられる。00年秋口からの長びいた世界的IT不況も、03年中盤から回復の兆しがはっきりしてきた。しかし、回復基調にあるIT需要には、不況突入以前とは大きな違いがあった。従って市場回復は、従来的ITの周期的な需要復活では説明しきれない。
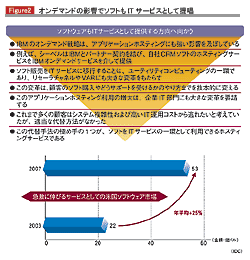 IT不況でIT投資が大きく削減されるなか、ユーザーの現行システムは抱える多種多様な問題が表面化して、ユーザーはこの解決を業界に迫り始めた。一方IT業界も、従来のように進化するITセクターの基盤技術が市場拡大を牽引する力が弱くなったことを感じていた。このためベンダーは、ユーザーの投資意欲を再び駆り立てる戦略の立て直しを迫られていた。
IT不況でIT投資が大きく削減されるなか、ユーザーの現行システムは抱える多種多様な問題が表面化して、ユーザーはこの解決を業界に迫り始めた。一方IT業界も、従来のように進化するITセクターの基盤技術が市場拡大を牽引する力が弱くなったことを感じていた。このためベンダーは、ユーザーの投資意欲を再び駆り立てる戦略の立て直しを迫られていた。巨大ベンダーであるIBMも同じ課題に直面しており、これの突破口として同社のサム・パルミザーノCEOは、オンデマンド戦略を発表し、これによって自社の高い成長を担保できることを狙った(Figure1)。
例えば、従来動向とは異なる需要の高まりの1つとして、これまで立ち上がりがみられなかったASPを含む、サービスとしてのソフト供給事業が米国でユーザーを急速に増やしている現象が挙げられる(Figure2)。
これまで市場が大企業に限定されていたCRM(顧客情報管理)が、シーベルなど有力ISV(独立系ソフトウェアベンダー)が自社ソフトをホスティングスタイルで提供し始めると、採用するユーザーが急増しているからだ。
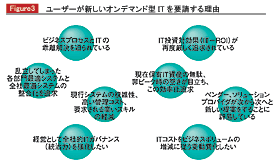 ■ユーザーの要請にIT業界が応える
■ユーザーの要請にIT業界が応えるIT不況の間、ユーザーでは現行ITが抱える問題がいろいろな側面で表面化してきた(Figure3)。
それはIT予算が削減されるなか、IT部門はこれまでも叫ばれていたTCO(所有総コスト)の削減、厳しいROI(投資対効果)追求に対する明確な解答を示すことができなかったからでもある。問題の基本的側面は、「企業のビジネスプロセスとITの一体化」に乖離が強く感じられることであった。IT購入費が安くなったことで部門最適化システムだけが乱立し、これが全社最適システムに収束しないことも経営から問題視された。
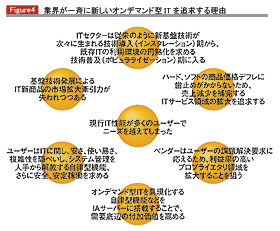 一方、システムはますます複雑化し、この管理コストも高く、システム担当要員にも高いスキルが要請されるようになった。また経済低迷でいろいろな経費が削減されても、ITコストだけはビジネスボリュームとは無関係に固定化されたまま残され、この変動費化も課題としてクローズアップした。
一方、システムはますます複雑化し、この管理コストも高く、システム担当要員にも高いスキルが要請されるようになった。また経済低迷でいろいろな経費が削減されても、ITコストだけはビジネスボリュームとは無関係に固定化されたまま残され、この変動費化も課題としてクローズアップした。ITベンダーから見ると、新しいIT商品へのユーザーの関心が薄れ、基盤技術発展による需要拡大牽引力がどんどん小さくなっていることがはっきりしてきた。これらに代わってユーザーの関心は、システムの複雑性や管理コストを削減すること、あるいはインターネットの普及によって処理量ピーク時の処理パワーも推定しにくくなり、このための過剰設備の無駄排除も重要な課題となった(Figure4)。
また価格デフレによる売上減少対策としても、付加価値の高いプロプライエタリ商品開発や、ITサービスのメニュー領域拡大に寄与する戦略推進をベンダーも迫られていた。こうしたユーザーとベンダー側の利害が一致したことが、オンデマンド型という新しいITコンセプトが勢いづいた理由である。
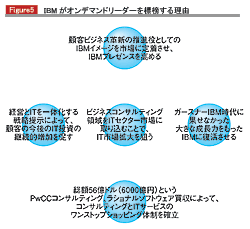 ■IBMにもオンデマンドを推進する背景が
■IBMにもオンデマンドを推進する背景が93年IBMのトップに就任し、巨額赤字の同社を短期間で再生したルイス・ガースナー氏が02年退任し、同年春にIBM新CEOにパルミザーノ氏が就いた。ガースナーIBMは利益では復活したが、この間の平均年売上高伸長は4%にとどまり、急速に拡大する世界IT市場でのプレゼンスは必然的に小さくなった。
このためパルミザーノ氏が率いるIBMは、ガースナー時代に果たせなかった高い成長に戻ることを投資筋から要求された。これに応えるためパルミザーノCEOは、03年からの大きな成長を株主にコミットした。しかしIBMも激しいハード、ソフト商品の価格デフレに抗することはできない。このため、これまでITセクターの市場ではなかった顧客ビジネスのコンサルティングにまで踏み込んで、自社ITサービス市場を拡大する必要に迫られた。
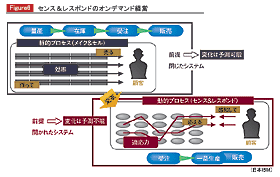 これを実現するためIBMは、巨額を投じてコンサルティング大手のプライスウォーターハウスクーパースコンサルティング(PwCC)と、新ITシステムに必要なソフト開発ツールに優れるラショナルソフトウェアを買収した。IBMはPwCC買収によって、ビジネスをオンデマンド型へトランスフォーメーション(転換)するコンサルティング力を備え、これと強力な自社ITシステム構築・運用を一体化し顧客に提供できるワンストップショッピング体制を確立した(Figure5)。
これを実現するためIBMは、巨額を投じてコンサルティング大手のプライスウォーターハウスクーパースコンサルティング(PwCC)と、新ITシステムに必要なソフト開発ツールに優れるラショナルソフトウェアを買収した。IBMはPwCC買収によって、ビジネスをオンデマンド型へトランスフォーメーション(転換)するコンサルティング力を備え、これと強力な自社ITシステム構築・運用を一体化し顧客に提供できるワンストップショッピング体制を確立した(Figure5)。IBMは自らオンデマンドと呼ぶ新しいビジネスプロセスに顧客が移行することを強く推奨する。IBMはこれまでの「メーク&セルの静的プロセス」であったビジネスを、「センス&レスポンドを標榜する動的プロセス」に転換することを客に要請するのだ(Figure6)。
- 1














