OVER VIEW
<OVER VIEW>オンデマンドコンピューティングの幕開け Chapter5
2003/09/29 16:18
週刊BCN 2003年09月29日vol.1008掲載
各ベンダー、オンデマンド時代の競合開始
■わが国ベンダー、SIerもオンデマンドへ向う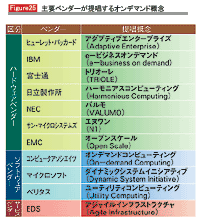 米国の有力ベンダーに続いて、富士通、NEC、日立製作所も相次いでオンデマンドコンピューティングについての自社コンセプトを提唱している(Figure25)。
米国の有力ベンダーに続いて、富士通、NEC、日立製作所も相次いでオンデマンドコンピューティングについての自社コンセプトを提唱している(Figure25)。NECは、自社コンセプト「VALUMO(バルモ)」に基づく技術を商品化して発売した。VALUMOで強調するのもIBMの「e-ビジネスオンデマンド」、ヒューレット・パッカード(HP)の「アダプティブエンタープライズ」と全く同様のコンセプトであり、コンピューティングの自律、分散、協調、仮想化の機能だ(Figure26)。
日米の有力ベンダーは、同じ視点から現行ITの問題点の是正とその延長線上に次世代コンピューティング像を提唱しているが、呼称はそれぞれ異るものの、狙いは全く同じだ。それだけ現行ITおよび業界構造にもたらす影響は大きい。
ガートナーは各社が同じ狙いをもつコンセプトを異なる呼び方にすることに異論を唱え、これらのITで実現する経営モデルを「ダイナミックエンタープライズ」と統一するよう提案している。
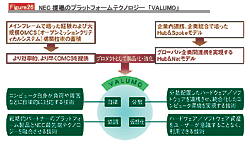 富士通の黒川博昭社長は自社の「TRIOLE(トリオーレ)」について、「たとえば、パソコンを客の注文仕様に基づいて組み立てる『ビルドtoオーダー』をシステム構築・運用とIT資源の配分までに持ち込む概念である」と説明する。
富士通の黒川博昭社長は自社の「TRIOLE(トリオーレ)」について、「たとえば、パソコンを客の注文仕様に基づいて組み立てる『ビルドtoオーダー』をシステム構築・運用とIT資源の配分までに持ち込む概念である」と説明する。また、NTTデータの浜口友一社長は新しいITについて次のように自説を述べる。「今後のエンタープライズシステムの狙いは、企業間、コミュニティ間を含めたeコラボレーションに絞られる。eコラボレーションが進化すると、その時点で刻々変化する『ダイナミックなバリューチェーンに対する付加価値創造の最適化』が果たせる。さらにeコラボレーションは組織や人だけでなく、IT資源間でも確立されるべきだ。サーバーを多数連携する『プロセッシンググリッド』や各部データベースを連携してそれぞれの目的に使えるようにする『データグリッド』は、リソースコラボレーションの典型だ」
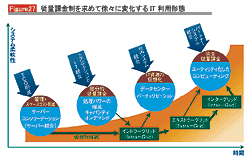 さらに浜口社長は、eコラボレーションを具現化するITインフラには、(1)柔軟な接続性、(2)高度な信頼性、(3)企業価値を保証する高いセキュリティ――の3条件が必要になるという。さらに同社長は、「このようなITをすべて企業が所有、運用、維持するのは困難だ。そのため企業ではコンピューティングパワーの『所有から利用へのパラダイムシフト』が起き、そのサービスの一環として電力と同じような従量課金のユーティリティコンピューティングへの需要が高まる」と説明する。
さらに浜口社長は、eコラボレーションを具現化するITインフラには、(1)柔軟な接続性、(2)高度な信頼性、(3)企業価値を保証する高いセキュリティ――の3条件が必要になるという。さらに同社長は、「このようなITをすべて企業が所有、運用、維持するのは困難だ。そのため企業ではコンピューティングパワーの『所有から利用へのパラダイムシフト』が起き、そのサービスの一環として電力と同じような従量課金のユーティリティコンピューティングへの需要が高まる」と説明する。■オンデマンドのロードマップを提示
IBMなど有力ベンダーは、オンデマンドコンピューティングの普及を急ぐため、これらコンセプトに沿ったハード、ソフトの商品、ITサービスの多様化を急ぎ始めた。自社ITインフラすべての所有を放棄して、すべてのコンピューティングパワーを従量課金制のユーティリティコンピューティングに移行するのは相当先の段階である。このユーティリティコンピューティングを究極のITサービスとしたうえで、有力ベンダー各社は現在各ユーザーで重要な課題となっているTCO(所有総コスト)削減のソリューションであるサーバーコンソリデーション(サーバー統合)に続くオンデマンドコンピューティングへのロードマップを明確に描き始めた(Figure27)。
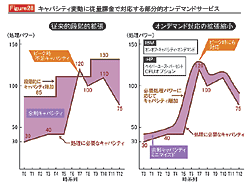 サーバーコンソリデーション自体も1台のサーバーを複数のサーバーに分割して使う仮想化技術の成果だ。一方、仮想化は多数分散設置されたサーバー、ストレージなどを仮想的に1台の機器のように運用管理するグリッドコンピューティングを実現している。グリッドも小規模のイントラ-グリッドに始まって最終的にはユーザーが処理パワーの不足を根絶するインターグリッドまで発展し、ユーティリティコンピューティングの基盤となる。
サーバーコンソリデーション自体も1台のサーバーを複数のサーバーに分割して使う仮想化技術の成果だ。一方、仮想化は多数分散設置されたサーバー、ストレージなどを仮想的に1台の機器のように運用管理するグリッドコンピューティングを実現している。グリッドも小規模のイントラ-グリッドに始まって最終的にはユーザーが処理パワーの不足を根絶するインターグリッドまで発展し、ユーティリティコンピューティングの基盤となる。現在、各ベンダーは従量課金を具現化したサーバープロセッサの増減やストレージ容量を増減できる商品の拡販に力を入れ始めた。サーバーでは処理量の増える時点で稼動プロセッサを増やし、処理が減ればプロセッサ数も減らす(Figure28)。
このような従量課金サービスをIBMは「オン-オフ・キャパシティオンデマンド」、HPは「ペイパーユース・パーセントCPUオプション」と呼び、特に米国で需要が高まっている。ストレージベンダーEMCはディスク容量の増減を従量課金で実現する「オープンスケール」サービスをわが国でも開始している。
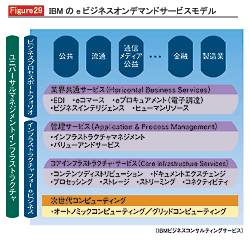 ■オンデマンドサービスのモデルを提供へ
■オンデマンドサービスのモデルを提供へIT業界の競合軸も完全に変貌しつつある。各ITベンダーはこれまでの「より高速」、「より大型」化コンピュータ開発競争から脱し、オンデマンドコンピューティング実現の技術開発、そしてオンデマンド時代のサービスモデルを市場に訴える競争を始めている。オンデマンドで先行するIBMは、商品だけでなくそのITサービスのモデルも提示している(Figure29)。
IBMモデルはインフラストラクチャとビジネスプロセスに大きく分けられている。インフラストラクチャではオートノミックとグリッドを基盤としている。ビジネスプロセスでIBMは、業界共通のeコマース、eプロキュアメントなどの他に、業種別ビジネスプロセスのアウトソーシング(BPO)を広く提供することを狙っている。
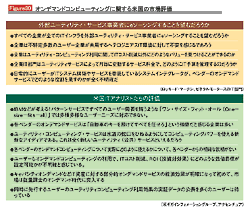 IBMは02年にコンサルティングのPwccを買収した。その狙いは企業がeビジネス主体のモデルへ、あるいはオンデマンド型経営への転換コンサルティングをその後のITサービスと一体化して提供することだ。こうしてIBMが02年秋にオンデマンド概念を提唱してから1年で、世界のIT業界は一気にオンデマンド競合に突入した。
IBMは02年にコンサルティングのPwccを買収した。その狙いは企業がeビジネス主体のモデルへ、あるいはオンデマンド型経営への転換コンサルティングをその後のITサービスと一体化して提供することだ。こうしてIBMが02年秋にオンデマンド概念を提唱してから1年で、世界のIT業界は一気にオンデマンド競合に突入した。これまでもIT業界は常に新しいコンセプトを基に変革を遂げてきた。まだ米国でも各ベンダーの提唱するオンデマンドに対しては期待とともに、ベンダーの言う通りにユーザーが動くのは危険であるとの警告、警戒の声も強い。従って、どのベンダーが自社提唱のコンセプトでユーザーのIT-ROIがどのように変化したのかの成果を実例で示すことを問われているといえよう(Figure30)。
- 1














