Special Issue
「“現場”のIT需要」がAIで急増、八子知礼氏とHPEが語るエッジコンピューティングビジネスの勝ち筋
2025/04/07 09:00
今回、長年にわたって現場のDXを最前線で支援してきたINDUSTRIAL-Xの八子知礼・代表取締役CEOと、「Edge-to-Cloud」のアーキテクチャーを掲げ、エッジから生まれるデータによる価値創出に取り組んできた日本ヒューレット・パッカード(HPE)のフロントパーソンに、エッジコンピューティングの最前線と、ITベンダーにとってのビジネスの可能性について聞いた。
クラウドとエッジの役割分担が明確に
―現場に近い場所でデータの処理を行う「エッジコンピューティング」という概念は10年ほど前から生まれていましたが、この数年で注目度が急速に高まっているように見えます。何が背景となっているのでしょうか。八子 2013年前後にIoTがトレンドになり、当時普及が加速していたクラウドコンピューティングと対比される形で、エッジコンピューティングという考え方が認知されるようになりました。IoTでは、クラウドとエッジの両方で処理が発生します。しかし、自動運転や工場内のマシン操作など、現場でリアルタイムな意思決定が要求される局面の場合、遅延が発生し得るクラウドは向いていません。このような用途では明確にエッジコンピューティングへシフトする動きが出てきました。クラウドの普及にあわせて、クラウドでは担えない分野を支えるエッジコンピューティング技術の普及も加速してきたと言えます。
小森 IoTが普及し始めたころを振り返ると、あまりパワーを必要としないワークロードで、即時の判断が必要なものだけをエッジで処理していました。それが昨今では、画像系データもエッジで扱うようになったため、IoTソリューションのエッジ側でもコンピューティングパワーを必要とするようになりました。また、IoTの普及は製造業がけん引しましたが、かつて製造の現場では独自技術で作り込まれた機器が使用される傾向にありました。しかし、最近では自前で作り込むよりも「汎用製品を活用できるならその方がよい」という考えが広まり、汎用のアーキテクチャーで動くサーバーの導入が進んでいます。
八子 かつてエッジに置かれるのは機器の制御を目的とした産業用コンピューターや専用アプライアンスがメインでしたが、AIの登場で画像解析の必要が出てきて、ソフトウェアとハードウェアの分離が起きました。そこでハードウェアの部分は、コンピューターメーカーによる最適な性能の製品を入れようという流れになっていますね。
小森 現場向けのソフトウェアの開発者も、ある用途に特化したコンピューターより、Windows Serverなどの汎用性があるテクノロジーをベースとした製品にメリットを感じるようになってきていると思います。
―技術的な観点に加えて、DX機運の高まりや人手不足といった社会の状況も、エッジコンピューティングの盛り上がりに影響しているのでしょうか。
八子 かつてはITの世界でも、クラウドやエッジ、SaaS、AIなどソリューションをテクノロジーごとに分けて見る傾向があったと思います。DXではそれらが「デジタル」という言葉でまとめられ、会社やビジネスを変える、社会課題を解決する手段として全体で議論されるようになりました。その中で22年に生成AIが話題となり、AIが目や耳といった感覚器の部分だけでなく、話す、書く、描くといった出力の部分にも使われるようになった結果、DXには圧倒的な情報処理能力が必要となり、エッジコンピューティングも必要とされるようになったと考えています。
お客様からは、大きく三つの意識の変化を感じます。まず一つは、ホワイトカラーだけでなく、現場でもデジタルを使って何かをしたいという意識の高まり。そして、AIというトレンド。さらに、IT部門に加えて現場の人の一部が、エッジコンピューティングとは何かを理解し始めたということです。
小森 お客様からは、AIとの組み合わせで何かをやりたいという要望が圧倒的に増えました。その背景にあるのは、AIという技術の成熟に加えて、やはり人手不足という企業の問題が大きいですね。

代表取締役CEO
八子知礼

デジタルセールス・コンピュート事業統括本部
技術本部
コンピュート技術部
小森博之
製造業をはじめ、さまざまな業種で採用が進む
―エッジコンピューティングはどのような形で活用が広がっているのでしょうか。象徴的な事例をいくつか教えてください。八子 製造業は特に進んでいます。一例としては、製造ラインで製品の外側の傷をチェックする外観検査が挙げられます。従来は光沢がある素材に入った傷をカメラで判定するのは難しかったのですが、今はエッジ側にAIを組み込んだカメラとサーバーを導入し、大量学習させたデータを元に判断させています。当社が支援したケースだと、プラスチック製品の外観検査で、必要な作業人数が半分になりました。
もう一つは、建機・農機の自動運転領域です。このケースでは、自律・自動運転の動作を高度化させるためにファームウェアをOver The Air(OTA)でアップデートするためと、現場の状態をカメラで収集しデータを解析するために、エッジ側へコンピューティング基盤を設置しています。後者では、クラウドに上げていたときは20時間かかっていた処理が20分で済むようになりました。
仁平 HPEでは、さまざまな業種向けにエッジコンピューティングを支援しています。例えば直接のエンドユーザーとしての導入事例では、くら寿司様が店舗サーバーとして「HPE ProLiant MicroServer」を設置し、受付からセルフレジ、回転レーン管理、AIカメラを使った不正防止などの仕組みを現場で稼働させるために活用されています。成果として、自動化によって削減したコストを、食材の調達に回すことができているとのことです。また、くら寿司様は世界に向けて事業を展開されており、海外でもサーバーが調達できることや、国内で購入した製品の保証を海外でも受けられるといったグローバルでの保守性もご評価いただいています。
八子 エッジコンピューティングを提供する際に意識しなければならないのは、現場のニーズです。ITのマインドセットで関わろうとすると、現場で働く方々と齟齬が生じてしまいます。そうでなく、現場の課題や要望をしっかり把握し、それを踏まえて設備メーカーと協力しつつソリューションを提示していくことが重要です。
またコストについては、生産設備の場合は一度購入すれば後は減価償却の期間を考えるだけですが、ITはランニングコストがかかり、さらにトラブルが起こった際の対応も必要になるので、従来の製造業での購入とはお金の払い方が変わることをしっかり伝えつつ適切な提案を行っていく必要があります。

パートナー・アライアンス営業統括本部
アライアンス営業本部
OEM営業部
仁平貴之
HPE+パートナーソリューションで問題解決
―HPEのエッジコンピューティング向け製品が、パートナーのビジネスに成果をもたらしている事例はありますか。仁平 HPEでは、パートナー様がお持ちのソリューションと当社のエッジサーバーなどを組み合わせたビジネス展開を支援する「HPE OEMソリューション」という協業の枠組みを用意しています。例えば、自動車関連企業向けにナンバープレート認識システムを提供しているピー・エム・シー様では、自動車ディーラーに来店した車のナンバーを認識して顧客管理システムと連携し、接客担当者用のモニターに顧客の来店目的やこれまでの対応履歴を表示させることで、カスタマーエクスペリエンスの向上につなげています。当社はサーバーの安定供給体制に加えて、多拠点サーバーのリモート運用管理が可能な「HPE Compute Ops Management」をご提供することで、遠隔地に置かれたサーバーの効率的な保守対応をご支援しています。
また、知能ロボットコントローラーによる製造や物流の自動化ソリューションを手がけるMujin Japan様では、工場や倉庫内の搬送業務を自動化するAGV(無人搬送車)ソリューションを提供するにあたり、HPE ProLiantサーバーとHPE OEMソリューションを採用されました。同社では、最も効率的に搬送できるルートをリアルタイムに算出してAGVに自動走行の指示を出しています。
AGVは100台規模まで同時に運用できるものの、台数が増えるほど高いリアルタイム処理性能が要求されるため、エッジ側のサーバーで処理を行う形を採用されました。また同社では、早期導入を求める顧客に対応すべく、ある程度の台数のサーバーを自社で確保しておく必要がありました。HPE OEMソリューションでは、当社からの工場出荷時ではなく、サーバーを顧客エンドユーザー様に納入した時点から保守契約が開始される仕組みを備えています。製品の安定供給とあわせて、保守開始の柔軟性も選定時の大きなポイントになったとお聞きしています。
ITソリューションプロバイダーにとって大きなチャンス
―製品の提供だけでなく、パートナーがエッジビジネスを効率的に展開するための仕組みを用意されているということですね。その他の協業や支援体制としてはどのようなものがありますか。仁平 エッジコンピューティングの領域におけるビジネスは、お客様から求められる内容が一般業務系のシステムとは異なります。提案先はIT部門ではなく現場の事業部門(LOB)ですし、お客様がやりたいことを実現した上で、その仕組みを長く使っていけるものにしなくてはなりません。そのため、HPE OEMソリューションでは、通常よりも長期間の供給が可能な機種や、ファームウェアのアップデート間隔を極力最長化するサービスなどを用意しています。
小森 HPEのエッジ製品群は、ITパートナーやエンドユーザーの皆様も知見があるWindows Serverをサポートしているので、ソリューションの実装や運用は行いやすいはずです。最新のWindows Server 2025では、リブートせずに更新プログラムを適応できる「ホットパッチ」機能が備わったので、エッジで使う際にセキュリティー面でもより安心してご提案いただけるようになりました。現在、世の中では無人コンビニや医療におけるAIアシストなど、現場を革新する新たな取り組みがどんどん出てきています。HPEでも、温度範囲が広かったりほこりが舞っていたりする場所でも使え、さらにGPUも搭載できるなど、さまざまな環境で使える「HPE ProLiant DL145 Gen11」サーバーも用意しているので、パートナー様とともにエッジ領域で新たなビジネスに挑戦していきたいです。
八子 エッジコンピューティングが社会により幅広く実装されると、多数の機器を長期間運用するための知見が求められるようになります。その点HPEはITの世界で長期にわたり事業を展開し、知見も豊富にある、ナンバーワンプレイヤーだと思います。最近はDXがAIの文脈に置き換えて捉えられることが増えていますが、そうなると大規模なデータセンターをたくさん作ってリソースを供給するよりも、小さくちぎったAIの固まりをどんどん現場に置いていくほうが現実的な解決策になります。このコンピューティングモデルでは、ITソリューションを提供されるベンダーの手が届くところに、広大なブルーオーシャンが広がっていると見ることができます。HPEパートナーの皆様にも、ぜひこの大きな動きをキャッチアップしていただきたいですね。
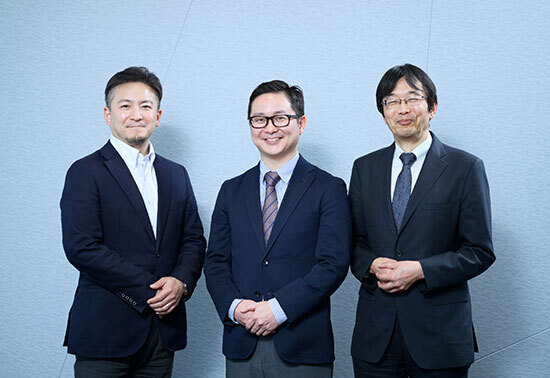
サーバーパッケージモデルのHPE SmartChoice及びフルカスタマイズCTOサーバーのHPE DirectPlus
それぞれでご提供しております。お取引のあるHPE販売特約店様にお問い合わせください。
HPE SmartChoice 構成いらずのラクラクサーバーパッケージ
https://www.hpe.com/jp/ja/hpe-smart-choice.html
HPE DirectPlus お好みに合わせてオンラインでサーバーをフルカスタマイズ
https://h50146.www5.hpe.com/directplus_ent/server/
HPE OEMソリューションに関してはこちらから
https://www.hpe.com/jp/ja/oem.html

本記事でご紹介している導入事例はこちら
くら寿司様
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00143722jpn
ピー・エム・シー様
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00131864jpn
Mujin Japan様
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00141511jpn
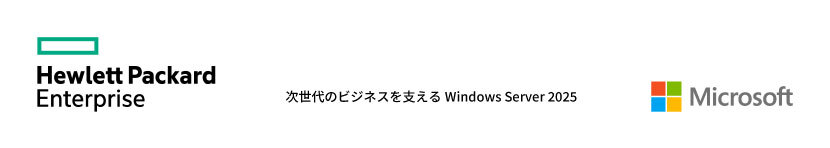
- 1
関連記事
水冷GPUサーバーの販売増へ 生成AI需要とDC受け入れ整備が後押し
日本ヒューレット・パッカード、本番環境での生成AI活用を支援 コストを抑えた仮想化ソリューションも
【2025年 新春インタビュー】日本ヒューレット・パッカード データ駆動型の変革を支援














