BOOK REVIEW
<BOOK REVIEW>『咒の脳科学』
2025/04/04 09:00
週刊BCN 2025年03月31日vol.2053掲載
言語の海のなかに生きる存在
咒(まじない)とは呪文や念仏から「痛いの痛いの飛んで行け」と唱える“おまじない”に至るまで、人間の認知に影響を与える言葉であり、「個人のみならず集団、社会に深く影響をあたえるものである」と、音声言語の認知を専門にする筆者は指摘する。七夕の短冊や絵馬に願い事を書くのは、言葉によって観念的な願いを具体化する行為だという。ただ、実際に言葉にしてみると「こんなことがしたいわけじゃない」「何か違う」と、心の内に秘めた願いと、耳や目で感じる現実とのギャップに直面することも少なくない。鏡に映る自分の姿を認識する“鏡像認知”のプロセスに通じるものがあるとも。
新薬開発の治験で偽薬(プラシーボ)と本物の両方使って効果を確かめる手法があるが、往々にして偽薬でも何らかの変化が見られるプラシーボ効果は、言葉による認知の変化と捉えることができる。逆に毒薬だと嘘をついて偽薬を飲ませると、本当に具合が悪くなるノーシーボ効果もあるという。
人間は「物理世界に存在している生物ではあるが、認知という観点から見れば、言語の海のなかに生きる存在である」と筆者はいう。本書ではいにしえの言霊の力を脳科学の観点から解明を試みている。(寶)
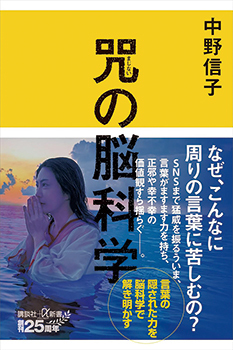
『咒の脳科学』
中野信子 著
講談社 刊 990円(税込)
- 1














